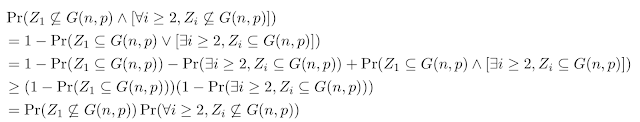本記事では, パラメタ化計算量の分野で有名な乱択アルゴリズムとしてcolor coding[4]を紹介し, その「脱乱択化」の方法 (perfect hash family) を紹介します.
1. color coding
1.1. 背景 (k-PATH)
1.2. アルゴリズム
1. 与えられたグラフ $G=(V,E)$ の各頂点をランダムに $k+1$ 色で塗ります. つまり, 各頂点に対して$\{1,\ldots,k\}$から一様ランダムに一つの値を選択しその値の色で塗ります.

2. 色付きグラフ $G=(V,E)$ がカラフルな k-path を含むかどうかを判定します. カラフルなk-path とは, 長さkのパスであって各頂点の色が全て異なる (i.e., $k+1$ 種類の色全てを含む) ようなものです. もしカラフルな k-path を含んでいたら, 元のグラフ $G$ は k-path を含むので終了し, そうでなければステップ1に戻ります.
1.3. アルゴリズムの解析
与えられたグラフ $G=(V,E)$ が k-path を含んでいたとして, その頂点を $v_1,\ldots,v_{k+1}$ としましょう. これらの $k+1$ 個の頂点がカラフルになる確率は
$\frac{k!}{k^k} \approx \sqrt{2\pi k} \exp(-k) \leq 3^{-k}$
となります (スターリングの近似を用いました). したがって上述のステップ1-2を $9^k$回繰り返したとき, パス$(v_1,\ldots,v_{k+1})$が毎回カラフルにならない確率は
$(1-3^{-k})^{9^k} \leq \exp(-3^{-k}\cdot 3^{2k}) = \exp(-3^k)$
となり, 非常に小さくなります (ここでは $1+x\leq \mathrm{e}^x$を用いました). つまり非常に高確率で, $9^k=2^{O(k)}$回の繰り返しの中で一回は k-path はカラフルになり, ステップ2で検出されるので高確率でk-PATHを解くことができることになります.
1.4. カラフルなk-パスの検出
動的計画法を使ってカラフルなk-パスの検出を $O(2^k\cdot n^3)$ 時間で解くことが出来ます. 二頂点$u,v\in V$および色の集合$S\subseteq \{1,\ldots,k+1\}$に対して配列として
$\mathrm{T}[u][v][S]:=$頂点$u$から$v$への, $S$-カラフルなパスが存在すればtrue, そうでなければfalse.
と定めます. ここで $S$-カラフルなパスとは, $|S|$個の頂点からなるカラフルなパスで, 各$c\in S$に対して色$c$で塗られた頂点を一個だけ含むようなものです (下図参照).
色つきグラフ$G$において$N(v)$で頂点$v$の隣接点の集合を表し, $\chi(v)\in \{1,\ldots,k+1\}$で$v$の塗られた色を表すこととします.
すると, $\mathrm{T}[u][v][S]$に対して以下の漸化式が成り立ちます.
$\mathrm{T}[u][v][S]=\bigvee_{w\in N(v)}\mathrm{T}[u][w][S-\{\chi(v)\}]$.
basic caseとして $\mathrm{T}[v][v][\{\chi(v)\}]=\mathrm{true}$ と定めます. また, 自明ですが$\{\chi(u),\chi(v)\}\not\subseteq S$ならばT[u][v][S]=falseです. これにより, カラフルk-パスの判定は$O(2^kn^3)$時間で解けるので, アルゴリズム全体では$9^k\cdot n^3=2^{O(n)}\cdot n^{O(1)}$時間で解けます ($n$の右肩の値はおそらく$2$になると思いますが, 大雑把に見積もっても高々$3$なのは明らかなので今回はそう記しました).
1.5. その他の問題への応用
k-PATH以外にもk-CYCLE (長さkの閉路の検出問題) といった問題も color coding を応用したアルゴリズムによって $2^{O(k)}\cdot n^{O(1)}$時間で解くことができます. 一般に, 入力で与えられたグラフ$G$が頂点数$k$の別のグラフ$H$を含むかどうかは 全探索により$O(n^{k+O(1)})$時間で解けますが, color codingを使うと $2^{O(k)}\cdot n^{O(\mathrm{tw})}$ 時間で解くことが出来ます (twは$H$の木幅です). したがってtwが定数ならば$2^{O(k)}\cdot n^{O(1)}$時間で解けます.
1.6. k-PATHに対するより早いアルゴリズム (advanced topic)
P≠NP予想より強いETHという予想を仮定すると, k-PATH問題は$2^{o(k)}\cdot n^{O(1)}$時間では解けないことが知られています[1]. 今回紹介したcolor coding では$9^k\cdot n^3$時間でしたが, 解析をちゃんとやると $O(\mathrm{e}^kn^3\log n)$時間でwith high probability (i.e., 適当な定数$\epsilon>0$に対し確率 $\geq 1-n^{-\epsilon}$) で正解するアルゴリズムになるはずです. では, 例えば$2.3^k\cdot n^{O(1)}$時間で解けるのでしょうか?
結論から言うと, $2^{k}\cdot n^{O(1)}$時間の乱択アルゴリズムが存在します[2]. このアルゴリズムは
1. 「グラフがk-pathを含まない iff Pは恒等的に0」となる多項式Pを構成する (但しガロア体$\mathrm{GF}(2^{\lceil 4k \rceil})$上の多項式).
2. Schwartz-Zippelの補題を用いてPが恒等的に0かどうかを乱択で判定する (その際に包除原理を用いる).
という流れです. Schwartz-Zippelの補題については相馬 輔 さんによる こちらのページで証明も含めて紹介されています. 更に, 現在では$2^{0.75k}\cdot n^{O(1)}$ 時間アルゴリズムも知られています[3].
この$2^{k}\cdot n^{O(1)}$時間アルゴリズムは様々な道具が登場し非常に面白いものなので, 機会があれば紹介したいと思います.
2. 脱乱択化 (derandomization)
脱乱択化とは文字通り「ランダムネスを排除する」ことです. これまで考えていたアルゴリズムは高確率で正解を計算するものでしたが, 脱乱択化をすると必ず正解を計算するアルゴリズムになります. 計算量理論では, 多項式時間の乱択モンテカルロアルゴリズムで(高確率で)解ける問題のクラス (BPP) が多項式時間で決定的に解ける問題のクラス(P) と等しいかどうかは未解決ですが, 多くの研究者はP=BPPだと信じているようです. P=BPPならば多項式時間乱択アルゴリズムは多項式時間のまま脱乱択化できる, ということになります. ここでは, それに関連したポジティブな結果の一つとして, 先ほど紹介したcolor codingの脱乱択化の方法について紹介します. キーワードはperfect hash familyです.
2.1. color coding is revisited
color codingに基づくアルゴリズムは
(i) グラフを$k$色で塗る.
(ii) カラフルな部分グラフを動的計画法で$2^{O(k)}\cdot n^{O(1)}$時間で見つける.
(iii) 見つけたい部分グラフが(i)でカラフルになる確率が$\geq 2^{-O(k)}$となるので, $2^{O(k)}$回(i)と(ii)を繰り返す.
というものでした.
即ち, 「見つけたい部分グラフが(i)でカラフルになるような塗り分け」をランダムネスを使わず決定的な方法で見つけられたら脱乱択化になります.
2.2. Perfect hash family
入力で与えられるグラフを$G=(V,E)$とし, その頂点数を$n=|V|$とします. そして塗り分けの集合 $\mathcal{F}$ を考えます. $[m]:=\{1,\ldots,m\}$と表すことにすると, 各要素 $f\in \mathcal{F}$は写像$f:[n]\to [k]$となり, $f(v)$は頂点$v$の色を意味します. つまり$\mathcal{F}$は写像の集合になります.
定義.
$\mathcal{F}$ が以下の条件(*)を満たすとき, $\mathcal{F}$は $(n,k)$-perfect hash familyと呼びます.
(*) サイズ$k$の任意の部分集合$S\subseteq [n]$ of $|S|=k$ に対して, ある$f\in\mathcal{F}$が存在して, $f(S)=[k]$となる (i.e., 塗り分け$f$の下では$S$はカラフルになる).
$\mathcal{F}$ を $(n,k)$-perfect hash family としましょう. グラフ$G=(V,E)$が入力で与えられたとき, $\mathcal{F}$を構成して全ての$f\in \mathcal{F}$のそれぞれに対してcolor codingの動的計画法のアルゴリズムを使ってカラフルな部分グラフを判定すれば, $T(n,k)+|\mathcal{F}|\cdot 2^{O(k)}\cdot n^{O(1)}$時間で決定的に解くことが出来ます. ここで$T(n,k)$は$\mathcal{F}$の構成にかかる時間です.
$(n,k)$-perfect hash familyについては以下の結果が知られています[4]:
定理.
$(n,k)$-perfect hash family $\mathcal{F}$で
$|\mathcal{F}|\leq \mathrm{e}^kk^{O(\log k)}\log n$
を満たすものを $\mathrm{e}^kk^{O(\log k)}n\log n$ 時間で構成することができる.
これにより, color codingの脱乱択化を$O(\log n)$時間程度のロスでやることが出来ます.
参考文献
[1] D. Lokshtanov, D. Marx, and S. Saurabh. Lower bounds based on the Exponential Time
Hypothesis. Bulletin of the EATCS, 84, pp.41–71, 2011.
こちらのサーベイ論文は(題目通り)ETHやSETHの基づいたlower boundとその証明テクニックを幅広く紹介しており, 大変良い論文です. SETHについては以前の記事で紹介しています.
[2] R. Williams, Finding a path of length $k$ in $O^*(2^k)$ time, Journal Information Processing Letters, 109-6, pp. 315-318, 2009.
color codingではk-PATHを$\mathrm{e}^k n^{O(1)}$時間でしたが, こちらの論文はSchwartz-Zippelの補題を用いて$O(2^{k}n^{O(1)})$時間でk-PATHを解くアルゴリズムを提案しています.
[3] M. Cygan, F. V. Fomin, L. Kowalik, D. Lokshtanov, D. Marx, M. Pilipczuk, M. Pilipczuk S. Saurabh, Parameterized Algorithms, Springer International Publishing, 2015.
パラメタ化計算量に関するアルゴリズムを幅広く紹介しています. FPTといった計算量クラス基本的な定義やW-階層といった困難性のクラスやそれらに基づくlower boundについても載っています. 各chapterの後ろには豊富な演習問題とBibliographic notesが載っており, ここには計算量の改善の歴史などが載っています. 誤植もあまりなく, 英語も読みやすいため個人的には非常にオススメの本です.
[4] N. Alon, R. Yuster, U. Zwick, Color-coding, J. ACM, 42-4, pp. 844-856, 1995.
color codingを提案した非常に有名な論文です. 論文中では$k$-CYCLE (長さ$k$の閉路の検出) を用いてcolor codingのアルゴリズムを説明していますが, それのみならず, 木幅が定数のグラフの検出, perfect hash familyを用いた脱乱択化についても書かれています.